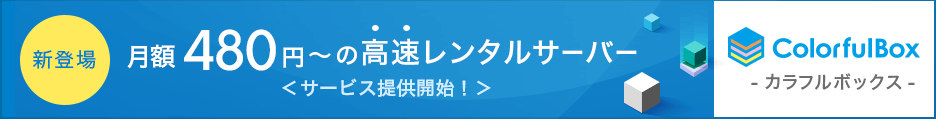ドイツ北部、ニーダーザクセン州の州都。中世に公国となり、1866年まで独立王国を形成していた。人口52万0900(1992)。中位山地と北ドイツ平原の境界に位置し、石灰岩、カリ塩、石油などの天然資源に恵まれる。ライネ川とミッテルラント運河が市内を通り、ルール地方とベルリンを結ぶ東西方向と、ハンブルクとフランクフルトを結ぶ南北方向の交通幹線の交差点にもあたる交通の要地。第二次世界大戦後、旧西ベルリンと連絡するための空港も建設された。機械、自動車、ゴム、事務用品、食品などの工業が盛んである。商業では卸売り、銀行、保険などの業務が行われる。また、1947年以来、毎年工業見本市が開かれる。州と連邦の諸機関があるほか、経済や宗教団体の本部や事務所、研究所やケストナー博物館、工科大学などの文化施設も多い。1235年に成立したブラウンシュワイク・リューネブルク公国を起源とする。同公国はウェルフ家のニーダーザクセンの領地から形成されたものだが、その後たびたび離合集散を繰り返し、一部はブラウンシュワイク公国として分離した。残余の旧領再統合はウェルフ家支流リューネブルク家に属するカレンベルク侯国(首都ハノーバー)のエルンスト・アウグスト1世が実現した。彼はさらに1692年選帝侯の地位を獲得し、以後のハノーバーの発展の基礎を築いた。次代のゲオルク1世は、母がイギリス王ジェームズ1世の孫であったことから1714年イギリス王ジョージ1世となった(ハノーバー朝)。以後、このイギリスとの同君連合関係は1837年まで続くが、その間、ハノーバー選帝侯はイギリス王としてロンドンに常居し、軍政を除くハノーバー内政は総督と領邦議会にゆだねられ、実質的には貴族の寡頭支配のもとで比較的に自由な統治が行われた。領土も、18世紀初頭スウェーデンからブレーメン侯国その他を獲得して北海にまで達し、また1737年設立されたゲッティンゲン大学は全ヨーロッパ的名声を博した。ナポレオン時代に南部がウェストファリア王国に併合され、北部はフランス領となったが、ウィーン会議で東フリースラントその他を獲得して王国への昇格が認められた。1819年諮問機関としての二院制議会をもつ憲法が制定されたが、貴族の寡頭制支配は変わらなかったので、フランス七月革命の影響で各地に暴動が起き、その結果ダールマンら自由主義者の協力を得て33年新憲法が制定された。新憲法は、37年イギリスとの同君連合が終わって即位したエルンスト・アウグスト2世により、ゲッティンゲン七教授事件などの抗議を排して破棄されたが、48年の革命の際に再度一時採用された(1848~55)。革命後は反動政治が復活し、対外的には関税同盟への抵抗(結局1854年加入)などプロイセンに対抗したが、プロイセン・オーストリア戦争に際しオーストリアに味方したため、66年プロイセンに併合されて71年ドイツ帝国の一部となった。第二次大戦後は一時イギリス占領下に置かれ、ドイツ連邦共和国成立とともにオルデンブルク、ブラウンシュワイクなどとともにニーダーザクセン州を構成してその一員となった。旧市街はライネ川の渡河点に発生した集落が中世に発達したものであるが、第二次大戦により被害を受けた。戦後、大胆な交通計画によって旧市街が改造され、中心部には広い街路が走り、周囲を環状道路が取り囲んでいる。大戦で歴史的建造物も損傷を受けたが、マルクト教会(1349~59)、旧市庁舎(1435~80)、かつてのハノーバー公の居館ライネ宮殿(1636~40建築、1817~42再建)などが、戦後、補修・再建された。市内には公園や緑地も多い。〔小学館『スーパー・ニッポニカ』より抜粋、一部加筆修正〕
|